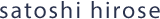Tra-Mite
| 英文 (290.43KB) | ||||
| 伊文 (206.99KB) | ||||
個展リーフレット
1998年12月
Tra-Mite,Hyperion Arte contemporanea, Turin
テキスト ダリオ・サラーニ (イタリア語、英語/ 日本語翻訳)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRA-MITE
トラミテ
ダリオ・サラーニ
作品の外観を完成させるにあたって、廣瀬智央はさまざまなメディアをつかう。インスタレーション、環境への介入、パフォ−マンス、彫刻、写真、絵画、そしてより大きな意味でのプロジェクトなどだ。こうした彼の、多様かつ多言語的な側面によって、彼は一つの作品の中にかなりの数のコンセプトや異なる理論をひきよせ、同居させる。動き、不安定さ、変わりやすさ、漠然とした、軽やかさ、自由気ままな、はかなさ、これらはすべて、作家がそのイコノロジカルな探究心を動かすのに刺激を感じる命題である。彼の作品におけるコンセプチュアルな要素は確かに際立っているが、それはさしあたり享受するにすぎない、わかりやすいアプロ−チであって、コンセプトに固執するのでもなければ、難解でもなく、むしろ明快で自然なものである。
廣瀬は純然たる本質的な日常性を、芸術的なレベルへと移転させる作業を行う。そしてそれこそが、まちがいなく、彼のすべての作品の中に一貫してみられる特徴である。シンプルな品々、その多くは毎日の生活の繰り返しの中で、ほとんど“目に見えない”ようなもの。それらのものが、事物間のル−ルについて、あるいは、シニフィエとパロ−ルの狭間を分析のうちに覆い尽くそうとするシンボルの意味について、システマティックな思考からなる一つの仮説をたてることで、主語(または補語)としての位置に置かれることになる。
廣瀬は東京生まれ、日本人の作家だが7年前からイタリアで生活している。彼はまた、頻繁に世界のあちらこちらを旅しており(その多くは招かれた展覧会の準備のためなのであるが)、そうした土地で出会うさまざまなリアリティや、住民同士のしきたりや習慣、そしてその地方の風習などに対する、非常に注意深い観察者でもある。観察し、そして異文化間の推移を体験しながら、自身の作品を実現するために推敲する。例えば、「Arlecchino(アルレッキ−ノ)」(1998)において彼は、イタリアの文化、伝統、そしてイタリア文学におけるもっとも典型的なモチ−フである存在を、寓意として用いた。互いに結びつけられた、様々な色の三角形の布からなるパッチワ−クが、展示室の上部、ちょうど観客の頭上にはりめぐらされている。この吊り下げられた作品は、ほとんどそれと気づかないような昇華された仕方で、コメディア・デッラルテの、議論の中心となる人物を喚起させる。ゴルド−ニの戯曲のなかの、二人の主人をもつ、悪党で詐欺師である召使いとして描かれたアルレッキ−ノから、ずるがしこいが深い部分では正直で、良識も持ち合わせた、非常にインテリジェントな庶民としてのアルレッキ−ノに至るまで、廣瀬はこの仮面のうちに、皮肉で、辛らつな表情を見出す。アルレッキ−ノはまた、人々を結びつける結合力という価値存在をも体現している。狂気に駆られた、長続きしないム−ブメント。自分自身を風刺しながら、作家は私たちの文化に属する、このふざけてばかり居ながら、感受性の強いパ−ソナリティに自身の姿を見出し、訪れた観客を、彼自身と他の人類学上に投影された彼の姿の仲介者として位置づけるのである。パッチワ−クのアイディアは、他の属性や、意図、心理的な投影を伴って、再び「Un gusto passegero」(1994)に見出される。未公開の作品であり、今回初めて公の場で発表された。色とりどりの包みにくるまれた、約10キログラムのチョコレ−トが、くぼみと一体化した基底部に納められている。こうしたボンボンは、“Cri Cri”というトリノの典型的な菓子製品である。この作品の場合、チョコレ−トを収納している、作家自身の手によるコンテナ−の白い構造物と、アルプス地方の伝統的な既製品の、共存の場面に私たちは立ち会うこととなる。作家の手作業による製作過程を経て、この場に重々しく存在するミニマルな構造体の凝ったつくりと、製菓工場で大量生産される“Cri Cri”の間の、一体、何が関係であり、境界線であるのか、作家は観るものに問いかけるのである。さらに、廣瀬は美学的な知覚の分野に、“味覚”という要素をも取り入れるが、これもまた彼の他の作品にも見受けられる重要な、感覚上の特徴である。
昨年、東京で初めて発表された「レモンプロジェクト03」では、ギャラリ−の部屋全体の床が、1万個の本物のレモンの“絨毯/自然”によって完全に覆われ、部屋の壁も、このレモンの自然な色合いとほとんど同じ黄色で塗られた。その空間に足を踏み入れながら、観客は直ちに目の眩むような黄色い色彩にだけではなく、レモンの強烈なにおいに捕らえられる。ステンレスと強化ガラスでつくられた、ステップを渡りながら、観客は部屋の一方からもう一方へとたどりつき、そこで早速、レモンのフレッシュジュ−スを振る舞ってくれる作家と対面することになる。この周囲を巻き込むインスタレ−ションに、私たちは多数の、複雑なコンセプトの注釈をみつける。
こうして、アルレッキ−ノや、トリノのチョコレ−ト同様、レモンという“要素”は私たちの島国の寓意となるのである(ゲ−テもまた、イタリアをレモンの花咲く国と呼んだ)。実はこの柑橘類の香りは、レモンの香料の入ったスプレ−によって助長されたものであり、感覚の方向性を見失わせる目的で、作家によって仕向けられたものなのである。感覚を不安定な状態にさせるゲ−ムは、この場合、自然と人工との関係にある。居合わせた人々は、自然の香りをかいでいるものと信じているのだが、実際は、人工的に抽出されたレモンの香料が、あらかじめ部屋の空気中に撒かれている。しかしながら、スプレ−の中にレモンから抽出した100%自然のエッセンスが含まれるていると知ったとき、再びこの人工的な感じは減少する。役割の交換、二元性、二重性のメカニズムはこうして、うまくとり行われる。広瀬は、彼の作品における重要な要素である“嗅覚”を、1994年に導入しており、翌年には、タイの東屋の床の表面に、この地方で頻繁に使われる香辛料の一つである香り高いカレ−の粉を、何百キログラムも敷き詰めるというインスタレ−ション、“スパイスル−ム”を行った。
真実と虚偽、自然と人工、現実と想像上のもの、それらの間の関係性については「Bocca d’oro(金の口)」(1993)において見事に処理されている。白い大理石でつくられた乳鉢の内側のくぼみの部分に、純金の箔とまがいものの金箔が混じったものが貼られている。当然のことながら、この混合物の中に、二種類のものの違いを見出すことは不可能である。そしてこれが、広瀬の語り口なのである。一般的でどこにでもある、私たちの生活の一部分を成すものが、目に見えるモデルとして選ばれる。乳鉢という一つの形を有するものが、科学の分野、医学の分野、そしてキッチンでも使われ、それ自身のうちに、互いに非常に異なったさまざまな心理的な投影と、想像されうる種々の状況とを含むことになる。一つのイメ−ジのもつ象徴の不確かさに関わる問題を取扱い、一つの閉じられた形から、存在の持つ転換可能なコンセプトへと連続的に推移して行く実体について、それは語っている。1989年から1994年の5年間を掛けて製作が進行していった「Architettura senza architetti(建築家なしの建築)」は、示唆にとんだ作品である。一室の床にさまざまな幾何形態の、白く塗られた無数の木片が散布されており、その印象はさながら、ミニチュアの建物の連なりだったり、縮小版の都市計画のためのマケットあったり、架空の未来都市の郊外に設定された、ある一区画の模型であったりする。この“フィクション”という非常に含みのある要素については、この場合もやはり“定義しがたさ、あいまいさ”、あるいは、“事物の見せかけの確実さのなかに潜む、不確かさ、物事のリアリティのなかに生来備わっている、隠された意味”といったものと、よく照らし合わせて考えてみる必要性があるだろう。
個々の人類学的な所属に関係なく、人類の遺伝のコ−ドに記されている、信念というものの気まぐれさは、「Isola occidentale(西洋の島)」(1994)において際立つ。大理石の一枚の板の上に、鮮やかな緑色の苔植物でつくられた三つの異なる大きさの円が配置されている。廣瀬がこの作品を思いつくに至るある種の刺激を感じたのは、世界の政治劇の可逆性について考えたならば、非常に不安定なものである、さまざまな地図に表れている国について考えていた時であった。西洋の地図においては、ヨ−ロッパが平面球形図の真ん中にあるのに対して、東洋においては、アメリカとヨ−ロッパの間に位置するのがアジアなのである。
空のシリ−ズ(ミラノ、ロ−マ、トリノ、シュツットガルト、バンコク、アンダルシア、シベリア...)において、作家は近年訪れたいくつかの国々の、はるか頭上に、雲と色彩の微妙な揺れとともに、ひらけている空間を写真に収めた。この写真のシリ−ズにおいて、今という瞬間のはかなさを、作家はほんの一瞬のシャッタ−の動きによって固定させている。空を定義するとしたら、それは自然の中のもっとも変化しやすく、移り変わりやすい存在と言えるだろう。それは、彼の用語の広い意味においては、はかなさを表している。そのような考えに関して、この日本の作家は記している。「作品は皆、視覚化された内面のプロセスとして潜在的な動きの不安定な均衡の元にある。しかし、この創造的な力についてあからさまに語ったり、示したりするには決して至らずに。」
廣瀬智央の作品を一つ一つ分析しながら見てゆくと、この作家の携わっているさまざまな概念の容量は、かなりの規模を持った広がりを成す。それはリゾ−ム型の迷路、同心の迷宮であって、概念的な世界や自明性、精神的な接合を横断する鏡の永遠のたわむれである。さまざまな階級と種の問題を横切って駆けめぐり、問題と疑問を提起しながらも、決して一つの答えを与えることがない。すべてが一つの、地理上、所属上の交差点にあり、現実的なものから、メタフィジカルなものへと向かう旅の途中にあって、精神的であると同時に、合理的に現存している。
彼のインスタレ−ションは、シニフィアンとシニフィエに圧力をかけて、記号論を無化してしまう力を持ち、事物はもはやそれらの実際の機能とは無関係に存在し、このように新しく、新鮮で、みずみずしい、生まれたばかりの実存となる。
美的で全体的な体験により興奮した五官とともに、私たちが彼の作品の中にいるとき、私たちを迎え入れるものは、エネルギ−である。彼の作品に対面して、私たちが納得させられるのは、ユングの言葉によれば、“シンボルとは、エネルギ−のベクトルである”ということであろうか。しかしそれは心理的で控えめな、軽妙でわずかなエネルギ−であり、決して強すぎたり、攻撃的であることがない。そして、それこそが、まさに「tra−mite」において感じられる軽快な印象であり、この作家の作品をつないでいるリンクであり、作品全体のあらましをみる中で用いられる要素の持つ、揮発性なのだ。こうしたコンセプトについて、廣瀬自身が書いている文章を引用するのは非常に興味深いことである。「透明という軽やかさや、重量の除去という軽やかさへの理解は、芸術の詩学的側面と言える。さらに思いがけないユーモアとアイロニーがある(...) 。軽やかさとは、相反する重さまでも含み、重さと軽やかさの間、精神と身体の間を行き来し、活き活きと移動する。軽やかさは、すぐれた事だけれど安易な事に陥るのではない。多くの場合、長所は短所でもあるようにパラドキシカルなもので、相反するものが絡み合い、どこで一つがおわって他が始まるのか分からない。」
この短い、最後の数行において、廣瀬智央の全作品を解釈するためのコ−ドに導く「tra mite(媒介)/tra(間) - mite(柔和な )」は明らかにされることであろう。
ダリオ・サラ−ニ(美術批評)
トリノ、イペリオン・アルテ・コンテンポラーネアでの廣瀬智央「TRA-MITE」展テキスト、NOV.1998.
(宇津木彩 訳)